イチジク君 もうこんなに(@_@) 2020/4/15

実がつくと嬉しいものです(^^♪
でも、果樹は後から収穫しやすいように樹形を整えることが大切。
素人の私たちにそれができるか、これから一生懸命に勉強しなくっちゃね。
イチジクは聖書にもよく登場する植物です。
おいしく食べながら読んでみたいもんです(笑) (K)

![[イメージ]](https://www.ryujo.ac.jp/blog_office/wp-content/themes/ryujo-office_2020/img/image.jpg)
ブログページ

実がつくと嬉しいものです(^^♪
でも、果樹は後から収穫しやすいように樹形を整えることが大切。
素人の私たちにそれができるか、これから一生懸命に勉強しなくっちゃね。
イチジクは聖書にもよく登場する植物です。
おいしく食べながら読んでみたいもんです(笑) (K)

既にご紹介した中庭のリニューアル。
4階から眺めると、こんな感じです。
「ただいま成長中」ということで、立ち入り禁止のロープが張ってありますが、十分に育った段階で取り外します。
よく見ると、写真の下の方から上に向かって、芝の緑が濃くなっていますよね。
そう‼ 下の方ほど建物の影に影響されて成長が遅くなるのです。

実は、緑化を設計した方も、この点を心配していたのです。
「本当に芝が全面に育つのだろうか?」と。
でも、チャレンジしたわけです。
生き物の世界ですから、やってみないと分からないことって結構多いのです。
後は、私たちの管理がどこまで行き届くかにかかっています。
芝の手入れは大変なことは分かっています。
でも~~~、チャレンジ‼
これが楽しいんだわ(^o^)/ (K)

美しくて迫力がありますね、やはり。
一発花火って感じですがね(*_*;

わたしとしては、目立たなくとも長~~~く咲いてくれる方が嬉しいのですが、でも、アクセントとしては、チャーリップの存在は欠かせませんよね(^^♪
それでも、保育者としては、一発屋さんよりも、地道にコツコツ毎日を大切にする生き方の方が、たぶん、子どもの成長に良い影響を与えると思います。

「やるときは、やるよ!」てな傲慢さは、どうしても避けたいですね。
「できるのなら、普段から、ちゃんとやっとけ(笑)」 (K)

現在、桜の木は敷地の南側にしか存在しません。今回のキャンパス整備計画において、正門付近のものは全て伐採されてしまいました。新校舎を建てるための苦渋の決断だったのです。
何度もご紹介したように、南側は学生さんの動線からは遠く外れています。だから、写真は何とももったいない風景なのです。
でも、これも長い歴史を持つ本学の名残の1つですから、大切に大切に。
こうやって気軽に記録に残しておくことも意味があるわけです(笑)(K)

サクランボの花が散ったな~と思っていたら、いつの間にか、ほら、もうこんなに実が付いていました(*_*;
葉の茂り具合が貧弱だから、このまま全部が成熟するとは思えませんので、念のため、追肥をしておくことにします。
一方、イチジクの方は、日に日に葉が大きくなっていることが分かるくらいの成長スピードです。

ここ南門周辺は正門ではないので学生さんの往来はありません。駐車場を利用する人や業者さんが主に利用するのみです。
だからと言って手を抜くわけにもいかず、クローバーやワイルドフラワーによる緑化に2018年5月から取り組み始めて、だんだんと環境が豊かになってきました(^^♪
大学の評価は、もちろん、教育の中身で決まりますが、その中身が校内美化整備への取り組み具合で何となく分かってしまっても困りますので、決して疎かにはできませんよね。
地道な作業がこれからも続きそうです!(^^)! (K)

ホームセンターに夏の花苗が所狭しと並ぶ季節になりました。そこでは、たいてい、ペチュニアが主役を務めているものです。
そんな小さな苗たちを横目に(?)中庭のピンクのペチュちゃんはすっごい勢い(笑) ドーム状に広がったその直径は1mはあります。
以前、知多で見つけた早春のペチュニアをご紹介しましたが、あの時に感じた「いつか、柳城にも」との願いが2年目にしてかないましたよ(^o^)/ 感謝ですっ‼
といっても、特別な管理をしたわけではありません。たまたま暖冬だったことが幸いしたのでしょう。冬をすんなりと越せれたので、一年間同じ姿で成長できたということです。
ただし、あえて言えば、花壇なので、肥料は少なめに与えることを心がけました。ペチュニアは雑草のようなワイルド性を持った品種ですので、路地では、その性質が遺憾無く発揮できるのです。
願いはいつかはかなうもの。理想のイメージを持ち続けるから、きっとそうなっていくのでしょうね。
そんなプチ体験ができました(^_-)-☆ (K)

66年の歴史を持つ名古屋柳城短期大学に、この4月、四大が併設されました。
名古屋柳城女子大学。晴れの船出です。
もちろん、ちまたで流行する新型コロナウイルスの影響で、今日の入学式は大幅に縮小されはしましたが、それでも、本学院の大きなチャレンジが今日から始まったのです。
チャレンジには困難さが伴ってこそ、その意味があります。今までの繰り返しだけでは、同じ結果以下しか期待できません。聖書にある「新しいブドウ酒は、あたらしい皮袋に入れるものだ」という精神を発揮するチャンスが、キリスト教主義を貫く本学にもいよいよ与えられたと、むしろ感謝して前に進みたいものです。
夢と希望とを持って入学してくれた新入生の皆さんが、柳城を誇りに思って巣立っていけるよう、私たちスタッフも持てる能力を最大限に活かしていきます。
小さな努力を毎日坦々と続けることが成功への秘訣。植物を愛してやまなかった創設者のマーガレット・ヤング宣教師の心を大切にする意味には、計り知れない深さがあるように感じます。(K)

園芸美化サークル・マーガレットのメンバー全員が晴れの卒業を迎えたため、新年度のサークルの存続が怪しくなってきましたが、そんなことには関わりなく、植物たちはハツラツと生き続けています。こちらも図太くならないとね!(^^)!
【YM】
柳城短大に入学して夏あたりがら、園芸活動をしていたIさんとKさんの婆が目に止まり、薗芸をやってみたい!と思い、私も一緒に活動するようになったのが始まりでした。
園芸を全くやったことがない私にとっては、花摘みなどで屈んだ姿勢で長時間いることや穴を掘るなどの作業が本当に辛かったです。なので最初は休憩ばっかりしていました(笑)が、毎日の積み重ねで体力をつけることができたし、体重を落とすこともできました(笑)
特にKさんには厳しい指導を受けて、うんぎりしたりやる気をなくしかけたこともあったけど、私のことを思って言ってくれてる、言ってくれることを感謝しなければならないと思い直して、限界まで頑張ることができました。
この活動を通して、自分自身の体を変えることができたし、心と体両方の忍耐力をつけるこもできました。園芸サークルに入って本当に良かったと思います。園芸サークルのメンバーの方に出会えて私は本当に感謝しています。
本当に本当にありがとうございました。

【SO】
わたしは友達の勧めでこのサークルに入りました。
最初どれも初めてで失敗ばっかりで辛く悔しかったです。慣れて来る度に少しづつではありますがコツをつかみ、園芸はもちろん折り紙制作も上手にできるようになり嬉しかったことを今でも鮮明に覚えています。
私は柳城祭実行委員会に所属していたので、サークルの方はあまり活動することができませんでしたが、部員をはじめ顧問の先生方、1年間ありがとうございました。この経験は保育園で活かすことができるので、子どもに伝えていきたいです。
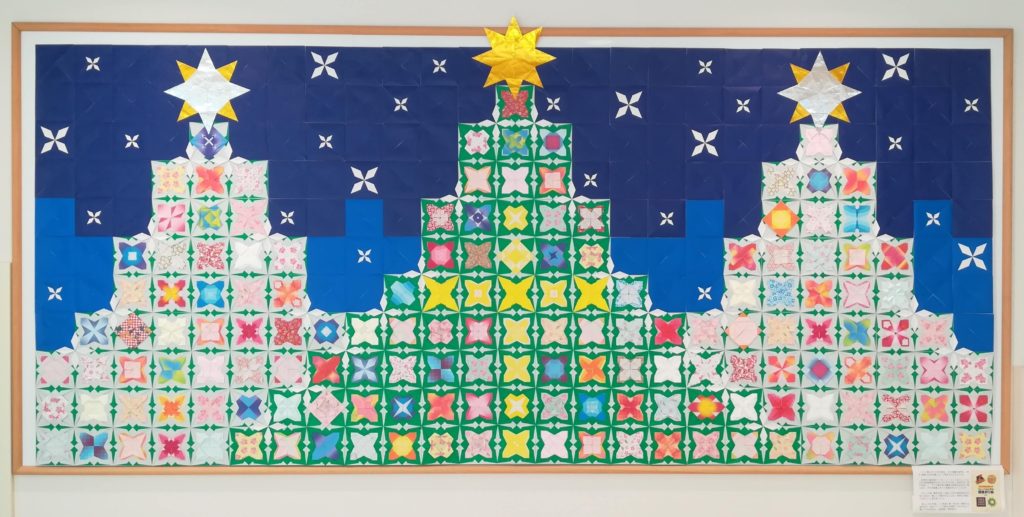
【Y】
いよいよ私たちが柳城短大から巣立つ時が、やって来ました。
保育科2年次の春から始めた園芸活動です。
私は、はじめは花柄を摘むと、ふくら脛が筋肉痛になったり、花柄の先だけ摘んでしまい、ビオラが針山のようになったりと園芸のど素人でした😊✨
振り返ると活動のはじめから一年間ぐらいは使命感、喜びが自分本位であったなぁと恥ずかしく思います‼️(^o^;)
しかし幾度もお花たちと一緒に季節を感じる毎に、また活動内容が多様になり深まるにつれ、私の筋力は不思議な早さで身体にも心にもついてきました。
そして今、卒業にあたり、私は確信しています! この3年間毎日、園芸活動で学んだ体験は、私のこれからの人生の「軸」となるのだと。
柳城学院の創立者ヤング先生は、一つのお花の姿から神さまの愛を子どもたちにお伝えになりました。
その学び舎に集う子どもたちの中に、子ども讚美歌『ことりたちは』が大好きな一人の女の子がいたんです。(歴史資料 JKU年次報告書に見る「柳城」尾上 明子・菊地 伸二著 研究紀要 (22), 165-202, 2000名古屋柳城短期大学 より)
彼女は心細い病の中、そして亡くなる前にも、幼稚園で教えてもらったこの讚美歌を愛唱なさっていたそうです。
私は柳城短大の卒業にあたり、この歌詞をヤング先生、お世話になったみなさま、仲間たちに捧げます。
ーこども讚美歌10番ー
うたのこえは ちいさくても
よろこびなさる かみさま


祈るエンジェルの像が、咲きそろいだしたチューリップに囲まれて周囲を清らかにしてくれていますね~~~!(^^)!
これは決して宗教の話ではありません。
祈りとは人間の本能に基づく行動様式の1つと捉えるからです。
人は祈りを通して、大いなるもの(人によっては神とか仏)に身を委ねます。その謙遜さが人を反省へと導き、それを土台に、新たな向上へと向かわしめるのです。
この反省と向上の繰り返しが成長のカギとなります。子どもの前に立とうと夢を描く柳城生には、是非とも身につけておいて欲しい「お約束」かもしれません。
柳城の花壇には、そんなメッセージが密かに(笑)整えられているのですよ(^_-)-☆ (K)

チューリップが咲きました‼ 昨年とほとんど同じ時期です。強烈な暖冬となった今シーズンだったので、3/17の卒業式に咲くかもと期待していたのですが。まあ、それよりも、冬を見事に越したペチュニアとマリーゴールドを見てください‼


マリーちゃん(黄色)の方は「息も絶え絶え」って感じでかわいそうですが、ペチュちゃん(ピンク色)の方は「これから爆咲するぞ」って勢いです(笑)

一方、果樹の方ではサクランボの花がプチプチかわいく咲いています。これが実へと成長していくですね。落ちてしまわないことを祈りたいです。
今年の年度末はキャンパス整備の最終局面にあたり引越や搬入が目白押しで、それこそ猫の手も借りたいくらいの毎日が続きます。それに園芸サークルのメンバーは全員が卒業してしまったので、これから先、花壇の管理が行き届かなくなるでしょう。
でもメンバーが愛してくれた花壇を何とか守りながら、そして植物に癒されながら、抜かりなく先に進んでいきたいと思います!(^^)! (K)

今日は卒業式‼
新型コロナウイルスの感染を避けるために、通常の式典と卒業パーティーは取りやめにして、代わりに、ゼミ毎に教室に集まって、証書等の配布を受け、お別れの挨拶を取り交わすことになりました。
終了後、別れを惜しむ卒業生の姿があちこちで見られました。花壇の花を眺めるゆとりは感じられません。そして「速やかに下校するように」と卒業生に向けて注意喚起をしなければならない担当者は、正に断腸の思いだったでしょう(*_*;
式典が中止になれば、事務職員が卒業生の晴れの姿を見るチャンスはスケジュール的に無くなります。それは余りにも過酷。大学とは教員と事務職員とが車の両輪のごとく機能して始めて成り立つ所だからです。

それで「少しでもアクションを」と思い、一輪ブーケを卒業生にプレゼントする作戦に出ました。総務課の提案で、これが認められて、急いで手配をしてギリギリのところで間に合いました。感謝です(^o^)/

花に添えられたメッセージは以下の通りです。
「ご卒業、おめでとうございます。
チューリップの花言葉は「博愛」
マーガレットの花言葉は「真実の愛」
本学院の創始者マーガレット・ヤングは花壇を大切にされた方です。彼女の「愛をもって仕えなさい」という「建学の精神」を学んだ皆さんの将来を期待して、これら2本の花を贈ります。 2020年3月17日 柳城短大 事務職員一同」
柳城を卒業したことを誇りに思えるような、そんな熱いハートを持った人に成長して欲しいと願います。(K)
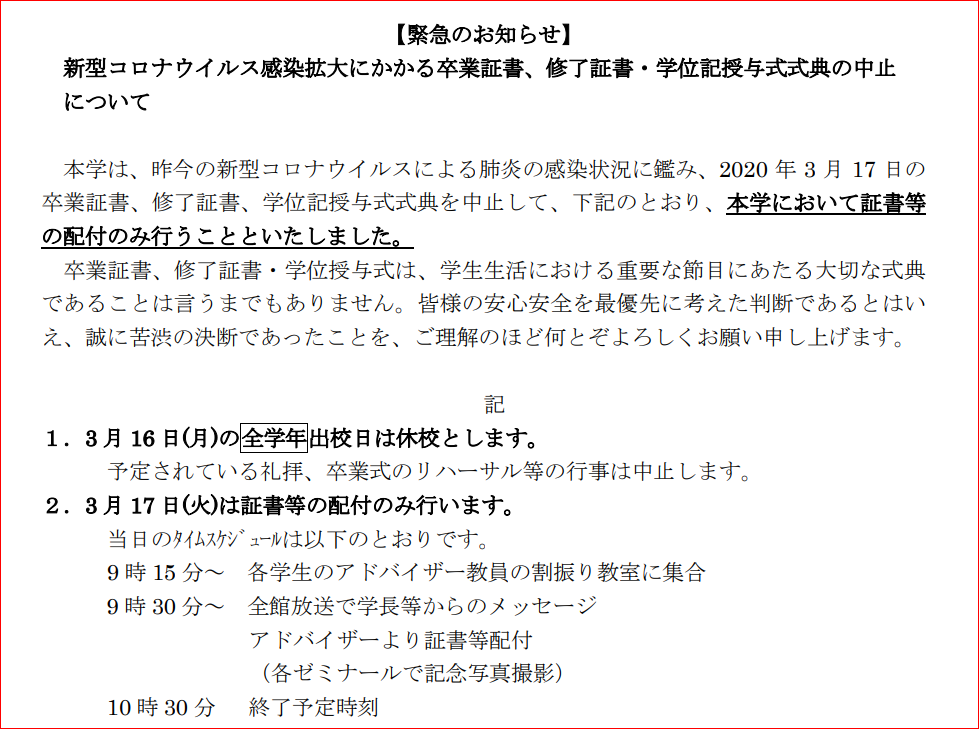

卒業式を明日に控え(笑)、今日は南側玄関付近に、さくらんぼ、ブルーベリー、いちじく、きんかん、ぐみの苗木を植えました。
以前から「短大の空いているスペースに、蝶や小鳥が集まる果樹園があったらなぁ」と思っていました。
甘~い野望ですが(笑)しっかり理由もあったんです。
柳城創設者のヤング先生は、フレーベル思想を胸に、この名古屋の地に幼児教育の礎を根付かせた方です。
当時の幼稚園の園庭には、さまざまな植物が植えられていました。
ヤング先生は子どもたちと一緒に果実を楽しむひとときも、心の育みの中に組み込まれていたと私は思います。
ですから私は卒業を前にして、「子どもたちのキラキラ輝く果樹園が欲しい!」そう思っていました。
今日の植樹は、そんな願いが聞きとげられ叶うことが出来ました。

植樹の体験は中庭を含め、二回目です。しかし今回は中庭に比べ大木になる果樹もあります。
この日のため春休みはサークル長と、ほぼ毎日南側花壇の土を掘り起こしていました。
そのお陰かな?土がとっても柔らかく感じました(^-^)/
「どんな実がつくのかな?」そんなことを話ながら、楽しい作業は進みます。

さぁ。最後の仕上げに、水やりを効率よくするため木のまわりに丸く溝を作り、ミッション終了です!
まさに…記念植樹(笑)
私たちは与えていただけた恵みに感謝し、大切な母校の「実り」をこれからも祈ります。(Y)

今の時期、幼稚園や保育園に就職を控えた学生さんらは、通常ですと、現場で事前研修があるため、何かと忙しいのですが、今年は、新型コロナウイルスの影響で、随分と研修が少なくなっているようです。
ウチのサークルメンバーも状況は同じですが、他とちょっと違うのは、現場研修が無くなった分、学校で何かを学びたいという意欲に駆られて、毎日のように登校している事。ピアノや歌の練習をメインにしつつ園芸活動にも精を出すというパターンで、充実したキャンパスライフを楽しんでいるようです(^^♪
それで今日は、校舎南側の清掃をしてもらいました。
というのも、つい最近、古いブロック塀が格子状のフェンスにリニューアルされたため、敷地内が道路から丸見えに(@_@) 柳城関係者の出入りが全くないこの緑化スペースは、とても褒められる環境ではなかったので、急いで、大きなごみだけは片付けようとしたわけです(*_*;
みすぼらしい状態を道路側から見られるのも悔しいし、柳城らしくもないので、3年くらいかけてキチンと環境を整えたいと思っています。
サークルメンバーさんのお陰で、新しいチャレンジがまた一つ始動します(^o^)/ (K)

キャンパス整備計画の最終段階として、ここ中庭の緑化工事が完成しました。
奥の白っぽい部分にはコウライ芝が張られています。そして手前の黒っぽい部分にはクローバーの種がまかれていて、すでに発芽が始まっています(^o^)/

芝生にはバトミントンのネットが張れるように整備されているため、のんびり日向ぼっことともに、ちょっとした運動もできるよう、配慮されています。
クローバーエリアは「遊びを学ぶ空間」です。保育者養成校にとって、とっておきのスペースに成長して欲しいな(^^♪
そして、上の写真の左校舎の脇にあるのが、柳城のメイン花壇である中庭花壇です。
実は、中庭の緑化工事計画を作る際に、中庭花壇を縮小させる案が出て、私は相当に心配をしました。結局、中庭花壇は柳城にとって極めて大切な場所だという確認がされて、現状維持が決まったという、そんな経緯があったんです。
長年にわたって、いろいろな方が苦労して守ってきた場所です。だから土も肥えていて、つまり生きているのです。このあたりの感覚が理解できるところが、今の柳城のちょっとした自慢かもね(^^♪ (K)

日当たり抜群の南側道路沿いの敷地には、多くの植物たちがひっそりと暮らしています。
昔はこの南側に正門があったので、その当時は、もっと手入れがされていたはずですが、今は、年3回、庭師さんらによる剪定や消毒、草刈りによって、最低限の美観が整えられています。
今、そこにある梅とスイセンが春を告げてくれています。

北門を利用して柳城に集う人々に、ほとんど知られることがない植物たちですが、校地の緑化面積を稼いでくれている貴重な存在には違いありません。
だから、もう少しまともに手入れしたいとチャンスをうかがっているところです。
そんな話を、園芸サークルのメンバーとも交わしている今日この頃です。(K)

黙々と(?)と作業するサークルメンバーを事務室の窓越しから激写だぞ~~~(^^♪
定植してから3か月近くになるのに、なかなか大きくなってくれずに心配していますが、草取りだけは欠かせません。リッピアが雑草に負けては困るからです。
寒い中でも元気に活動してくれるメンバーたちに、心から感謝です(^o^)/
「こんな地道な努力を経験できることが、保育者養成校の証の一つになるのだ」という強い信念が大切。
そう勝手に思い込んでいる私です。(K)

写真の中央部分です。見えますか? 花ではありませんよ(^^♪
そう、置物です。本(聖書?)を読むエンジェル。
柳城を愛する方からの嬉しいプレゼントなのです‼
順に増えていって、全部で5点になりました。
もちろん、キリスト教をベースにする本学に合わせてチョイスされた優れ物ばかりです。

この立像の下には…
“Amazing Grace how sweet the sound.”
『アメイジング・グレイス』の最初の歌詞が刻まれています。
「驚くべき(神の)恵み、何と美しい響きであろうか」

奥の石板みたいに見える板には
“Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Matthew 5:4”
「悲しむ人々は、幸いである、/その人たちは慰められる。マタイ5:4」
これら「驚くべき恵み」たちに、ひたすら感謝です‼
花壇のメッセージ性が強くなって、さらに柳城らしくなりました。
創設者のマーガレット・ヤング宣教師も、きっと涙を流して喜んでくださることでしょう(^o^)/ (K)

この花、1号館の東側の木陰にひっそりと咲いていたものを、スコップで掘り起こして中庭へ移植したものです。クローバーの種を蒔く前に除草剤を使う、その範囲に育っていたので、かわいそうと思い、事前に避難させたというわけです。
移植したのが6月頃でした。中庭は日当たりが大変よいので、そのためか、真夏にレンテンローズの葉が焼けたように枯れてしまい、とっても心配しました。でも、このように、見事に咲いてくれましたよ~~~(^o^)/
といっても、花のように見えるのは実はガクで、その中央にある雄しべみたいなものが本当の花なんだそうですよ(*_*; それにして、頭を垂れて咲く様子は、何とも慎ましいですね~~~。見習いたい人も多いのでは⁉
イエス・キリストの復活をお祝いするイースター(復活日:2020年は4月12日)の直前40日(レント:大斎節)頃に咲く、バラに似た花ということで名付けられています。クリスマスの頃に咲くクリスマスローズとともに、大切に大切にしていきたいと思います!(^^)! (K)

今日は学食の北側花壇にひそかに育つへデラ君を支柱に固定する作業を行いました!
へデラ君たちはのびにのびて♪いよいよ壁をこえそうです。
しかし!壁になにも、からまる支えが無かったため、せっかく伸びたヘデラ君の枝が花壇側に落ちてしまっていました。これでは夢に見た蔦の絡まる壁にはなりません。
そこでメンバーは考えへデラ君たちが、ひもを越えようとする力を活用する作戦に出たんです!

まず壁の内側に10本ほどポールを立てました。ポールにはひもを二本巻き、ひもの外側から壁へ、また内側から花壇に落ちないよう工夫をしましたよ(^o^)v
出来上がりはこんな感じ!
目標があれば、さらにまっしぐら!
育ち盛りのへデラ君たちです。

きっとあっと言う間に緑溢れる塀になるに違いありません!
みなさんも、ぜひ!その成長ぶりに注目していてくださいね~\(^o^)/💓 (Y)

1/20の大寒を越えた2/4の立春の頃に、今季最大級の寒気団がやってきて、名古屋では6日夜に今シーズン初めての氷点下(マイナス0.1℃)を観測しました。名古屋の冬日の初観測は、これまで2016年1月20日が最も遅い記録でしたが、今シーズンは、これより17日遅く、これまでで最も遅い初観測となりました(*_*;
2018年に名古屋で記録された史上初の40℃台の気温(40.3℃)が瞬間的に思い出されました。
こんな温暖化傾向にある昨今ですが、日本で冬を越せない多年草にとっては朗報かも。中庭で頑張っているペチュニアとマリーゴールドもそうです。本来は多年草で、数年にわたって咲く性質を持っているのに、日本では冬が厳しいので枯れてしまい、一年草扱いです。
このままの勢いで春を迎えて欲しいですね(^o^)/ (K)
